2018
病院の待ち時間を前向きに過ごす 「クリエイティブ・ホスピタル・プロジェクト」
宙(sora)・・・ 夜の病院がナイト・アートミュージアムに
●期間:平成 30 年 11 月 26 日(月)〜12 月 3 日(月)17:00~20:00
●場所:横浜市立大学附属病院(金沢区福浦 3-9) 2 階ロビー
●取材について:病院内での取材撮影が可能な日時は 11 月 27 日(火)17:00~20:00
現代美術アーティスト、曽谷朝絵(そやあさえ)さんのアートアニメーション作品「宙(そら)」を病 院 2 階ロビーの壁や天井に映像投影。
吹き抜けの大空間に巨大な色彩の森が出現し、夜の病院がナイト・アートミュージアムに変わる。
動き続ける森の空間を体感することで、患者さんやそのご家族、お見舞いの方など、病院を訪れた皆さんに非日常体験をしていただき、元気づけることを目的とした企画。

知らせるマスク・・・ ウイルスを視覚化するマスク
●期間:平成30年11月9日(金)〜11月16日(金)9:00~17:00
●場所:横浜市立大学附属病院(金沢区福浦3-9) 3階(エスカレータ上)
病院におけるコミュニケーションを象徴するアイテムを対象に、プロトタイピングを行う。
附属病院内での展示企画「知らせるマスク」「いないいない白衣」「ナースバード」 という3つの実例を通じて、今後、さまざまなヘルスケア課題に対してコミュニケーション・デザインが持つ力の可能性を発信していく。

マスクには、飛沫感染、接触感染によるウイルスの感染を抑える効果がある。特にこれらの感染は、人が大勢集まる場所で発生しやすくなる。
この一見かわいく見えるデザインは、実は感染するウイルスをモチーフにしている。ウイルスそのものがデザインになることで、ブロックするウイルスを理解する。マスクのデザインそのものが、流行するウイルスを教えてくれる「広告」の役割を果たすことで、周りの人も感染予防の意識も高まる。
物理的に感染を防ぐだけでなく、知覚的にも機能することで感染を防ぐマスクである。
※この取り組みは横浜市立大学附属病院 感染制御部が監修協力。
いないいない白衣 ・・・ 子どもに好かれる白衣

医師の着ている、白衣。元々この白には、汚れが目立つことで医療現場において清潔を保つという意味がある。しかし、子どもによっては「白衣=こわい」と感情が結びついてしまい、白衣を見ただけで泣いてしまう子どもも、少なくない。実際、大人でも、緊張が理由で血圧があがる「白衣高血圧」という症状がある。
この「いないいない白衣」は、緊張した医療現場の空気をやわらげるコミュニケーション・ツールとして、袖から飛び出した耳を裏返すと、大好きなカワイイ動物たちが、子どもの気持ちを落ち着かせる。
※刺繍は群馬県桐生市の(株)笠盛様が協力。
ナースバード ・・・ 聴き上手なトリ型ロボット

ナースバードは、あなたの健康状態を聞き出すロボット。
相手の痛みや悩みを詳細に聞き出すことで、症状や状態を把握する「傾聴力」は医療の現場でも大切なチカラ。お医者さんや看護師さんの白衣を見るだけで緊張してしまう「白衣高血圧」の人でも、ちいさなロボットになら話せてしまう。遠くない未来、診察前にナースバードが事前問診を行い、カルテに反映。診察時間が短縮されることで、病院での待ち時間も減らせるかもしれない。
<プロジェクトメンバー・クリエーター>
(株)電通 河瀬 太樹 アートディレクター/ビジョナー
中川 諒 コピーライター/プランナー
村上晋太郎 電通CDC
梅田 悟司 現インクルージョン・ジャパン(株)
取締役 コミュニケーション・ディレクター
2017
病院の待ち時間を前向きに過ごす 「こころまちプロジェクト」
●期間:平成29年12月4日(月)~(終了日時は未定)
●場所:横浜市立大学附属病院(金沢区福浦3-9) 2階ロビー・1階休憩室
院内での患者さんの待ち時間を「前向きな時間」にして元気づけることを目的として、東京デザインプレックス研究所(東京都渋谷区道玄坂2-10-7)とのコラボレーション企画「こころまちプロジェクト」を実施。
病院での待ち時間は長く退屈です。「あっと言う間に過ぎてしまうような楽しい時間を病院に。」そんな思いから生まれたのがこのプロジェクト。
院内で過ごす時間を心待ちにできるような時間、「こころまち時間」に変えることを目指し、若手クリエーターたちと協力して空間・グラフィック・WEBデザインによる5つの企画を実施。
Second Life Toys
●期 間 : 平成29年2月20日(月)~3月3日(金)
●展示場所: 横浜市立大学附属病院 2階ロビー掲示板前
「移植医療の普及啓発」と、院内での待ち時間に「患者さんを元気づけること」を目的として「Second Life Toys(セカンド・ライフ・トイズ)」を横浜市立大学附属病院で展示。
Second Life Toysは、壊れてしまった大好きなおもちゃと離れたくない、まだまだ一緒に遊びたいという子どもたちの願いを「おもちゃの移植手術」によって叶えるプロジェクト。展示期間中は、展示エリアにおいて、患者さんへのアンケートの実施及び、臓器提供意思表示カード等を配布し、臓器提供意思表示の啓発を行う。
2016
自分で想像するポスター
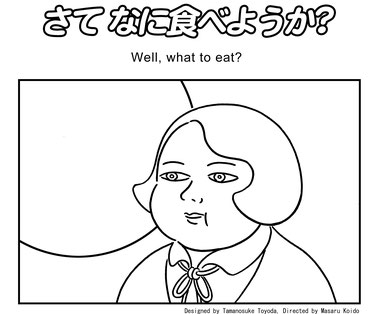

生活習慣病予防、認知症予防のためのToyoda Tamanosukeさんによる吹き出しを活用したアートデザイン。
Designed by Tamanosuke Toyoda, Directed by Masaru Koido
宙( そ ら) ・・・ アート作品の映像投影で患者さんたちに元気を
「Cheerful Wall」プロジェクトは、病院内の診療や検査の待ち時間に、患者さんたちを元気づけるための実験的な取組。
今回はその第一弾として、横浜市立大学大学院医学研究科 発生成育小児医療学の伊藤秀一教授らと連携し、現代美術アーティスト、曽谷朝絵(そやあさえ)さんのアニメーション作品「宙(そら)」を附属病院小児科待合の壁に投影。
「Cheerful Wall」プロジェクトを通して、診察等を待つこどもたちが笑顔で楽しむことにより、待ち時間や処置時の負担軽減につながる手法の確立を目指す。
効果測定を含めた実証実験の開始に向け、現在準備が進んでいる。

「宙- A-glow」 アニメーションの原画、
パネルに紙に水彩、2013

「宙(そら)」アニメーション投影
、2014、iscp (NY)


演劇クエスト ・・・ロールプレイングゲームで健康行動促進
横浜市立大学COC(Center of Community) 教員地域貢献活動支援事業 / 「地域の健康・医療問題解決へ向けたメディカルデザインハブの構築」

「演劇クエスト」は、「冒険の書」を片手に、物語の主人公となってロールプレイングゲームを楽しむ体験プロジェクト。
患者さんのリハビリにスポットを当て、医療の現場である病院を舞台に、通院・入院患者の健康行動を促す体験プロジェクトのプロトタイプ(試作品)である「演劇クエスト 幻惑のリハビリテーション編」を制作。
患者さんが冒険者として院内を探索するストーリーになっており、シナリオにある選択肢によって参加者はそれぞれ違うルートで、屋上から駐車場まで、いろいろな所を楽しみながら歩くことができ、リハビリ等の促進を期待。
Another Steps…つい上りたくなる健康階段

『Another Steps(健康階段)』は、一日中ラボに籠って研究に勤しむ研究者に、階段を上る中で、世界50か国もの天気情報をリアルタイムで提供。階段を使うことによって、外の世界の「今」を知るきっかけとなり、自然に健康づくりが促進される実験的な取組として、平成28年4月に先端医科学研究棟内において実施。
今後金沢八景キャンパスでも展開。

2015
MISTAS
塩分を控える。香りを引き出す。
その答えは、ミストにあった。
醤油を塩分過多の原因にしない。
健康志向の高まりによって、塩分の取り過ぎが社会課題になりつつある。特に日本人は、醤油や味噌などの発酵食品を日常生活の一部として取り入れているため、特に塩分摂取量が多く、高血圧をはじめとした生活習慣病の原因として問題視されている。醤油メーカー各社は減塩醤油の開発などを行っているが、根本的な解決に結びついているとはいい難い状況である。そこで私たちは、醤油差しのデザインを見直すことで、節塩につながるプロダクトを開発することを着想した。
醤油をかけるものから、吹きかけるものへ。
醤油のかけ過ぎに着目した、一滴単位でかける醤油差しは既に市販されているものもある。しかしながら、こうした製品では、濃い味に慣れてしまったユーザーの味覚を満足させることはできず、結果的に多くの醤油をかけてしまう可能性も高い。
そこで、少量でも味わいを感じてもらうために、醤油を霧状にして噴霧する効果に着目した。ミスト状になった醤油は空気中で瞬間的に酸化し、香りが高まるのである。こうして、私たちは醤油をかけるものから、吹きかけるものへとリ・デザインさせた。
また、醤油は凝固することがあるため、内部で凝固しても押し出せるよう、スプレーの噴霧圧を最適化させた。
使い慣れ親しんだテーブルになじむデザイン。
プロダクト自体は、日本人が使い慣れ親しんだ醤油差しの形状をベースにした。その理由は、醤油を吹きかけるという新しい行為への心理的ハードルを下げながらも、テーブルになじむデザインとするためである。また、今後の使用シーンとして、家庭だけではなく、寿司店や懐石料理店などの和食店に置くことも想定されるため、陶器に近い質感を持たせた。
ALERT PANTS
あらゆる手間を排除したウェアラブル・ヘルスケア・プロダクト
「面倒だと続かない」に向き合う。
WHOの報告によると、日本の肥満人口は、直近30年でおよそ2倍になっているという。こうした状況を受けて、健康管理を目的としたウェアラブル・デバイスが数多く発売されているが、デジタル機器特有の充電やデータ管理の手間から、途中で使用をやめてしまうケースが散見される。
そこで我々は、健康管理を行うには、面倒くささを一切排除した製品こそが求められていると考えた。その理由はいたってシンプルである。「人間は、健康の時には、健康を維持することに興味がない」からだ。
アナログに、イノベーションを。
デジタル・テクノロジーは便利な反面、充電やデータ整理の手間が掛からざるを得ない。その気づきから、アナログにこそイノベーションを起こすべきだと考え、アナログでありながら先進的なウェアラブル機器を作ることを目指した。
そこで注目したのは、自分の身体に一番近い衣類であるのパンツである。そのパンツにメタボリック・シンドロームの基準値である、ウエスト85cmを境にして色が変わる仕組みを組み込むことで、鏡に向き合う度に自分の体型変化を常に意識し、危険信号を発信し続ける「アラートパンツ」の発想に辿り着いた。
発売後、医学会で話題に。
表参道ヒルズ内に店舗を構えるMARK'STYLE TOKYOでの販売され、発売当日に売り切れるなど人気を博した。販売時には、本製品の理解と製品性を促すマネキンを制作。それぞれに本プロダクトをはかせることで、製品性を一目で理解できるようにした。
また、医学界において、ヘルスケアにおける広告的アプローチである「広告医学」の思想と共に、本プロダクトが報告されるなど、未病を促して、誰もが手軽に健康になれるプロダクト開発の必要性が、医療従事者より多くの賛同を得ている。
上りたくなる階段
広告医学ヨコハマプロジェクト実行委員会
広告医学プロジェクトは、健康寿命日本一を目指している横浜市と連携し、〝自然な健康行動の誘発〟を目的とした『上りたくなる階段(健康階段)』を開発、(株)横浜シーサイドラインの協力のもと、金沢八景駅と市大医学部駅の階段に設置をしました。
●期 間:平成27年2月17日~平成27年3月19日(約1か月間)
『上りたくなる階段(健康階段)』は、「上り」はついエスカレーター等を利用してしまい階段を使わない…という日頃の運動不足の解消を目的に、ユニークなデザインを施すことで、楽しみながら階段を上る運動を誘発することを目指しています。
金沢八景駅 設置後の様子(※階段の立ち位置によって見え方が変わります)
designed by TAIKI KAWASE & MIKO SAKAMOTO
働く人々の運動誘発パッケージ
横浜市立大学COC(Center of Community) 教員地域貢献活動支援事業
横浜市立大学では、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能強化を図ることを目的としたCOC(Center of Community)事業を推進しています。 今回、COC事業の支援のもと、企業での社員の健康増進策を実施しました。
社員に1日3分以上、運動をする習慣をつけさせたいという依頼に対し、大きく3つの企画を提案。
-1つは「社内の絶景スポット」。社内で眺望の良い場所を、トイレに掲示して紹介。休憩中にトイレに行くと、一つ上の階に絶景ポイントがあることが分かり、ちょっと階段を上ってみる、といったシーンが生まれることを期待したもの。
-第2は、スマートフォン用アプリ。階段を使わない、塩分の高い食事を取るなど、健康を損なうような行動を「敵」としてデザインし、倒していくオリジナルゲーム「健康怪談」のアプリを提供。また、ウエアラブル機器と組み合わせて、目標より多く階段を上ると、有名漫画家が描いた4コマ漫画が見られるなどのインセンティブ設計も行う。
-第3は、駅の階段のラッピング。会社近くの駅の階段をラッピングし、描かれた動物は何匹かというクイズを出題して、歩く人の興味を引かせる。横浜・八景島シーパラダイスが近いため、海の生き物などをトリックアートのようにひそませて、子どもと一緒に楽しめるデザインに。
これらの施策により、依頼企業の社員は、100人弱の平均値で1日50段ほど、階段を上る量が増える結果となりました。
引用:日経デジタルヘルス

image

image
2014
健康エントランスプロジェクト
企業社員および来訪者に健康への意識を高める事、その「きっかけ」を目的として企業エントランスでの展示・体験コンテンツを配置。『健康を手軽に、楽しく、見る、知る、体験できちゃう週間に!』という考えのもと健康FESを開催しました。


広告医学研究会 始動
広告医学研究会とは、さまざまな関係者(医療者・クリエーター・企業・自治体関係者・患者/家族など)とともに、医療におけるコミュニケーション課題の解決を目指す学術団体です。広告医学の考え方に基づき、ソリューションとなる方法論の具現化を目指し、継続的に議論する場を提供します。
第1回テーマ 「認知症における広告医学を考える会」2014.9.17
●基調講演 (19:10~20:00)
座長:井上 祥 先生(横浜市立大学)
『 認知症と広告医学』 演者:武部 貴則(横浜市立大学)
●ディスカッション (20:00~21:00)
座長: 井上 祥先生(横浜市立大学附属病院)、内門 大丈 先生(湘南いなほクリニック)
『認知症疾患におけるミスコミュニケーションの問題~広告医学による克服は可能か?~ 』
話題提供:「認知症の祖母と暮らして」西井正造(公益財団法人 木原記念横浜生命科学振興財団)
2013
働く人々の減塩誘発パッケージ
日本に多く見られる塩分の過剰摂取は、血管を傷つけ、そして脳卒中や心疾患に繋がっています。そうした背景をふまえ、日常的な生活で塩分量を意識することを目的に、企業社員食堂での減塩実験を実施しました。
今回は、食堂内での人々の動線上にあるさまざまなタッチポイントを活用し、食行動の変容を引き出す魅力的なアイテムを活用しました。具体的には、ポスターや、POPなどの啓発アイテムを制作し、戦略的に展開した結果、一日あたりの食塩摂取量を10%以上減少させることに成功しました。なお、2004年から英国で始まった減塩キャンペーンは1500万ポンドの費用に対して年間6000例の心血管死を抑制し、年間15億ポンドの経済効果を示したとされており、わが国でも大きな効果が期待されています。
designed by YUKI SUGIYAMA & TAKUYA MIZUTANI
2012
医学生と共に学ぶ「医療」の仕組み

横浜市立大学では、大学の基本方針の1つに「地域貢献」を掲げ、地域の課題に対して、教職員はもちろんのこと、学生による多様な地域貢献活動を推進しています。
このような中で、学部・大学院生活や課外活動などを通じて、自主的な探究心、外部との調整力、積極的な行動力などを育成するとともに、地域の活性化を図ることを目的に「学生が取り組む地域貢献活動支援事業」を平成23年度から実施しています。
この事業は、地域が抱える課題を実践的に研究・解決する学生による地域貢献に資する活動等を学内公募し、優秀な企画・活動・提案・プロジェクトに対して助成金を交付するものです。
引用元:横浜市立大



書籍「二十年先の未来はいま作られている 」
私たちの危機感――まえがきにかえて
第1章 いまなぜ未来デザインなのか
第2章 2030年自分たちの生きる未来を描く
第3章 僕たちはこの国の未来を信じている
――座談会
日本経済新聞出版社/2012年刊

2011
電通と博報堂の産学連携ラボ「MIRAI DESIGN LAB.」
「広告医学が拓く、新たな医療のカタチ 」(横浜市立大学 医学部医学科)
「MIRAI DESIGN LAB.」は、電通と博報堂がコミュニケーション・カンパニーの責務として、「そのアイデアが、未来を創る。日本を変える。」をフィロソフィーとして設立。その活動の第一期として、昨年、全国の大学生・大学院生から“2030年の社会”を想定したアイデアを募る「MIRAI DESIGN AWARD 2030」を開催。
2011年3月には「MIRAI DESIGN AWARD 2030」を受賞した大学生・大学院生4チームと共に、約9ヶ月間かけて“2030年の社会”に向けた構想を練った。
引用:HAKUHODO
































